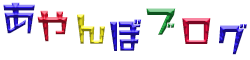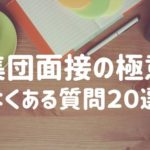こんにちは、元特別区職員のあやんぼです。
今回は、都庁と特別区の違いについてお話します。
この記事を読むことで、都庁と特別区の違いを理解することができ、自分がどちらを受験すべきか判断するための知識を得ることができます。
ちなみに、都庁や特別区の試験それぞれについて、もっと詳しく知りたい人はこちらの記事へどうぞ。
目次
都庁と特別区の違い【仕事内容】
はじめに、都庁と特別区の仕事内容の違いについてお話したいと思います。
都庁の仕事
総人口の1割が東京にすんでおり、予算の規模は47都道府県の中で群を抜いています。
ゆえに、他の道府県では真似することができないような、スケールの大きい仕事に携わることができます。
例えば、地方の大規模な計画策定、市町村を越えた広域的なインフラ整備や市町村への助言などを行います。さらに東京都は全国に先駆けた都市づくりや新しい制度の導入など、模範的な存在としての役割も担っています。
ゆえに、特別区のように地域住民と接する機会は少ないです。
しかし、当然ですが本庁以外にも出先機関があり、そこに配属されれば、地域住民と接する仕事をすることにもなります。
特別区の仕事
特別区は、地域住民と近い距離で仕事をします。
例えば、住民票の発行、子育て関係、生活保護、地域振興(お祭りのなどの企画運営)などがあります。
住民の人から感謝の声をいただくこともありますが、その分クレームも多いです。人と接することが好きな人は、やりがいを感じられるかと思います。
都庁と特別区の違い【給料】
都庁と特別区の給料の違いについてお話します。
都庁の給料
【初任給(事務・技術等)】平成31年4月1日適用
| 1類B(大卒程度) | 2類(短大卒程度) | 3類(高卒程度) | 1類A | キャリア採用 |
| 220,440円 | 188,520円 | 174,720円 | 240,240円 | 292,920円 |
【年収のモデル】平成31年4月1日適用
| 25歳係員 | 3,667,000円 |
| 35歳課長補佐 | 6,223,000円 |
| 45歳課長 | 10,206,000円 |
| 50歳部長 | 12,995,000円 |
特別区の給料
わかりやすく明記されれいるものがなかったので、こちらのサイトから引用します。
平均年収:720万円
部長職:1000万円~1200万円以上
課長職:960万円~1000万円
係長補佐:450万円~600万円
一般行政職:370万円~450万円
都庁と特別区の違い【難易度】
試験の難易度は、都庁の方が高いです。
しかし、問題のレベルが高いというわけではありません。私の感覚だと、都庁の教養試験と特別区の教養試験のレベルは同じです。
では、なぜ都庁の方が難易度が高いのか。
それは、都庁を志望する受験生の方が学力が高いからです。実際、特別区には東大出身の人は珍しい部類に入りますが、都庁だとそれほど珍しくはありません。都庁を目指す方は、覚悟が必要です。
とはいえ、教養試験でボーダーラインを超えることができれば、専門試験は何とかなりますよ。
都庁と特別区の違い【倍率】
都庁と特別区の倍率を比較してみましょう。
都庁の倍率
| 年度 | 採用予定数 | 申込者数 | 受験者数1次 | 合格者数1次 | 受験者数2次 | 最終合格者数 | 倍率 |
| 令和元年 | 290 | 3198 | 2276 | 掲載なし | 掲載なし | 403 | 5.6 |
| 平成30年 | 320 | 3637 | 2564 | 掲載なし | 掲載なし | 421 | 6.1 |
| 平成29年 | 340 | 3929 | 2751 | 1137 | 1093 | 439 | 6.3 |
| 平成28年 | 365 | 4529 | 2706 | 923 | 889 | 550 | 4.9 |
| 平成27年 | 484 | 5383 | 3465 | 1249 | 1207 | 640 | 5.4 |
| 平成26年 | 438 | 5186 | 3643 | 842 | 765 | 541 | 6.7 |
平成27年をピークに採用予定数、最終合格者が減少しています。
しかし、倍率は低倍率を維持しています。昨今の公務員不人気の影響です。オリンピック後の日本は確実に景気が悪くなります。そうすると、公務員人気が再燃してくるので、倍率が高くなることが予想されます。
今回の試験で「決める!」という覚悟で試験勉強をしましょう。
特別区の倍率
| 年度 | 採用予定数 | 申込者数 | 1次受験者数 | 1次合格者数 | 2次受験者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
| 令和元年 | 966 | 13296 | 11501 | 4244 | 3219 | 2032 | 5.7 |
| 平成30 | 1130 | 14998 | 12718 | 4505 | 3812 | 2371 | 5.4 |
| 平成29 | 980 | 15178 | 12683 | 4219 | 3599 | 2176 | 5.8 |
| 平成28 | 940 | 15574 | 11795 | 3433 | 2909 | 1781 | 6.6 |
| 平成27年 | 930 | 12534 | 9712 | 3263 | 2972 | 1739 | 5.6 |
| 平成26年 | 830 | 16078 | 12906 | 3031 | 2348 | 1668 | 7.7 |
前年度より採用予定数が減少しました。申込者数も減少しましたが、結果的に倍率は去年よりわずかですが高くなりました。とはいえ、平成26年、平成28年の倍率に比べると低倍率です。
都庁と特別区の違い【試験科目】
都庁と特別区の試験科目の違いです。
都庁の試験科目
都庁の1次試験は、教養択一試験、専門記述試験、論文試験です。
【教養択一試験】
| 科目 | 出題数 |
| 数的推理 | 6 |
| 判断推理 | 2 |
| 空間把握 | 4 |
| 資料解釈 | 4 |
| 現代文 | 4 |
| 英文 | 4 |
| 世界史 | 1 |
| 日本史 | 1 |
| 地理 | 1 |
| 思想 | 1 |
| 文学・芸術 | |
| 物理 | 1 |
| 化学 | 1 |
| 生物 | 1 |
| 地学 | 1 |
| 法律 | 2 |
| 政治 | |
| 経済 | 1 |
| 時事 | 5 |
【専門記述試験】
専門試験は記述式で、10科目の中から3科目を選択して解答します。
出題科目は以下のとおりです。
憲法、行政法、民法、経済学、財政学、政治学、行政学、社会学、会計学、経営学の10科目です。
特別区の試験科目
特別区の1次試験は、教養択一試験、専門択一試験、論文試験です。
【教養択一試験】
| 科目 | 出題数 |
| 数的推理 | 6 |
| 判断推理 | 5 |
| 空間把握 | 4 |
| 資料解釈 | 4 |
| 現代文 | 5 |
| 英文 | 4 |
| 古文 | × |
| 世界史 | 1 |
| 日本史 | 1 |
| 地理 | 1 |
| 思想 | 1 |
| 文学・芸術 | × |
| 数学 | × |
| 物理 | 2 |
| 化学 | 2 |
| 生物 | 2 |
| 地学 | 2 |
| 法律(社会科学) | 1 |
| 政治(社会科学) | 2 |
| 経済(社会科学) | × |
| 社会(社会科学) | 1 |
| 時事 | 4 |
特別区の教養択一試験の特徴は、数的処理の出題数です。40問中、19問が数的処理です。どの試験種でも数的処理は大事ですが、特別区ではさらに重要になります。
【専門択一試験】
| 科目 | 出題数 |
| 憲法 | 5 |
| 民法 | 5 |
| 行政法 | 5 |
| 刑法 | 5 |
| 労働法 | × |
| 商法 | × |
| ミクロ経済学 | 5 |
| マクロ経済学 | 5 |
| 財政学 | 5 |
| 政治学 | 5 |
| 行政学 | 5 |
| 社会学 | 5 |
| 社会政策 | × |
| 国際関係 | × |
| 経営学 | 5 |
| 会系学 | × |
| 心理学 | × |
特別区の専門択一試験は、問題選択解答制です。例えば、憲法を5問中4問解答して、マクロ経済学は苦手だから簡単な2問だけ解答するといったことが可能になります。
ですので、特別区を第一志望に考えている人は、広く浅くを意識して勉強をしましょう。逆に、国家一般職など問題選択制ではなく、科目選択制です。科目選択制とは、その科目を選択すると、その科目すべての問題を解答しなくはいけないということです。
つまり、国家一般職を第一志望にする場合は、ある程度、深く勉強をする必要があります。
まとめ
都庁と特別区の違いについてでした。それぞれについて、もっと詳しく知りたい方はこちらの記事を参考にしてみてはいかがでしょうか。
今回は以上です。
それではさようなら!